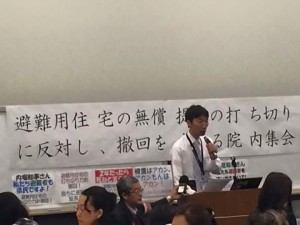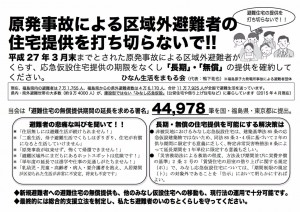< 裁判後の報告集会の様子 >
5月13日午前10時から、東京地裁103号法廷にて、福島原発被害東京訴訟・第11回期日が行われました。
法廷では、当方から、責任論についての国の主張に対する反論である準備書面(28)と、損害論の総論に関する準備書面(29)(原告らの精神的損害について)及びその関連証拠を提出しました。
一方、被告の東電からは、原告らの放射線被害に関する主張に対する反論である共通準備書面(7)及び関連証拠が提出されました。
その後、原告(原告番号8番さん)の意見陳述と,弁護団の平松真二郎弁護士による意見陳述が行われました。
以下で、原告の意見陳述の一部を抜粋して紹介します。
「私は今72歳です。2011年3月15日まで福島県田村市に住んでいました。でも故郷は福島ではありません。60歳まで神奈川に住み、東京で消費生活相談員として働いていました。夫は定年後は大地に根ざした暮らしがしたいと考えていました。そこで定年前に田舎暮らしをする土地を探し始め、1994年福島県田村市に9000平方メートルの土地を見つけました。その2年後地元の大工さんに頼んで在来工法の家を建てました。」
「1998年にまず夫が、私はその5年後に移住しました。夫婦二人で鍬で原野を開墾して、200坪の畑にしました。近所では牛を飼っていましたので、牛糞と敷き藁を積んで肥料としたものを分けてもらい、林から落ち葉を集めてきて、それも肥料にして畑に入れました。3年ほどすると、いい土になり、化学肥料を使わずともおいしい野菜が取れる様になりました。またその季節に合った野菜を作れば農薬を使わずとも育てられる、寒冷紗という目の細かいネットを使ったり、草を防ぐ防草シートを使ったりすれば、作業が楽になることも分かりました。」
「育てていた野菜は、たとえば茄子だけでも7品種でしたから、全部で50品種を超えていました。そのほかに黄色いキウイ、25本のブルーベリー、木立の中では椎茸や舞茸、なめこといった茸を栽培し、ほかに自生してくる山うどや蕗、たらのめ、わさびなどの山菜、栗があり、水がおいしく、まさに自然の恵みに感謝する日々でした。作業場に作った囲炉裏で、取れた野菜や山女を焼き、飲み、しゃべり、楽しい日々でした。夫は2007年に亡くなりましたが、私一人で暮らし続け、2010年にはキウイ39kg、ブルーベリー29kg、大豆16kg、クッキンクトマト53kg、いろいろな茄子120kgなどになり、またブルーベリーやイチゴからジャムを作り、千枚漬やキムチを漬け、大豆からは麹も手作りして味噌を仕込みました。」
「しかしこの暮らしは2011年3月11日で一変しました。最初は3キロ圏内の避難指示でしたが、それが10キロ20キロと私の家に近づいてくるのです。とにかく早く原発から遠ざかりたい、しかし高速道路は閉鎖されており、ガソリンも心もとなく、一人で一般道を長時間運転していくことに不安でした。」
「どうしようか考えあぐねていたところ、3月14日に電話回線が復旧しました。陸がだめなら空があると思い、福島空港に電話したところ、羽田行きの臨時便があると聞き、それから3時間復旧したパソコンの前に座って、その日はダメでしたが、翌15日の搭乗券を手に入れたのです。午後4時過ぎの便でしたから、15日は昼ごろ出て行けばいいと考えていたのですが、朝8時のニュースで東電の人が「職員は退避しました」と言っていて、私はこれは大変なことが起きたに違いないと思い直ちに犬を連れて車に飛び乗りました。国道288号線はガソリンを求める車で渋滞また道も分からず迷いましたが、なんとか昼ごろには空港にたどり着きました。羽田には長男が迎えに来てくれ、9時過ぎに都内の長男宅に着きました。東京都が用意してくれた被災者用住宅に入れることになったのは4月1日でした。」
「私の住んでいた地域は原発から30.5キロのところです。4月半ばになって田村市が詳細な地図を入手したところ20キロ30キロの円を描く円心がズレていたことが分かり、同じ大字の一部が30キロ圏内に入っていたことから、大字全体が緊急時避難準備区域に指定されました。これは9月には解除されています。
翌12年5月に校正されたサーベイメーターを借りて福島の家や敷地の放射線量を計りました。家の中は1m高さで1時間あたりほぼ0.4μSvだったのですが、二階の天井の下にサーベイメーターの検知部分を近づけると1時間あたり0.71μSvもありました。敷地ではケヤキの下が最も高く1時間あたり3.80μSv畑は大体1μSv前後でした。」
「帰れといわれてもこの砂だらけの畑に戻る気にはなりません。除染をしたからといって元の畑に戻ったわけではありません。年月をかけ豊かな土を作ったのに、これから有機栽培を再開するためには、山から落ち葉を集めてくるわけにはいかないし、近所から牛糞をもらってくるわけにもいかないでしょう。砂だらけの畑では前のような農作物を作れません。土も買わなくてはいけないでしょう。またまた長い年月をかけなくてはならないでしょうし、こういう畑の作物を喜んでくれるとは、とても思えません。
72歳の私がなぜそんな苦労をしなければならないのでしょうか?
夫婦二人の苦労を一度の事故で台無しにされ、孫をこの地で遊ばせる楽しみも奪われてしまいました。
私は被害者です。被害者がいて加害者がいないなどということはありえません。私のような被害にほかの誰かがあわないためにも、責任はきちんととって頂きたい。
国や東電に私の被害の救済を求めます。」
原告の意見陳述が終わると傍聴席から自然に拍手が起きました。
法廷が終了すると、近くの日比谷図書会館で報告集会が行われ、弁護団から法廷の説明と、参加者からの発言がありました。
今後の予定は,
2015年 7月15日 10時~ 東京地裁101号法廷
2015年 9月18日 10時~ 東京地裁101号法廷
2015年11月11日 10時~ 東京地裁103号法廷
です。傍聴をよろしくお願いします。